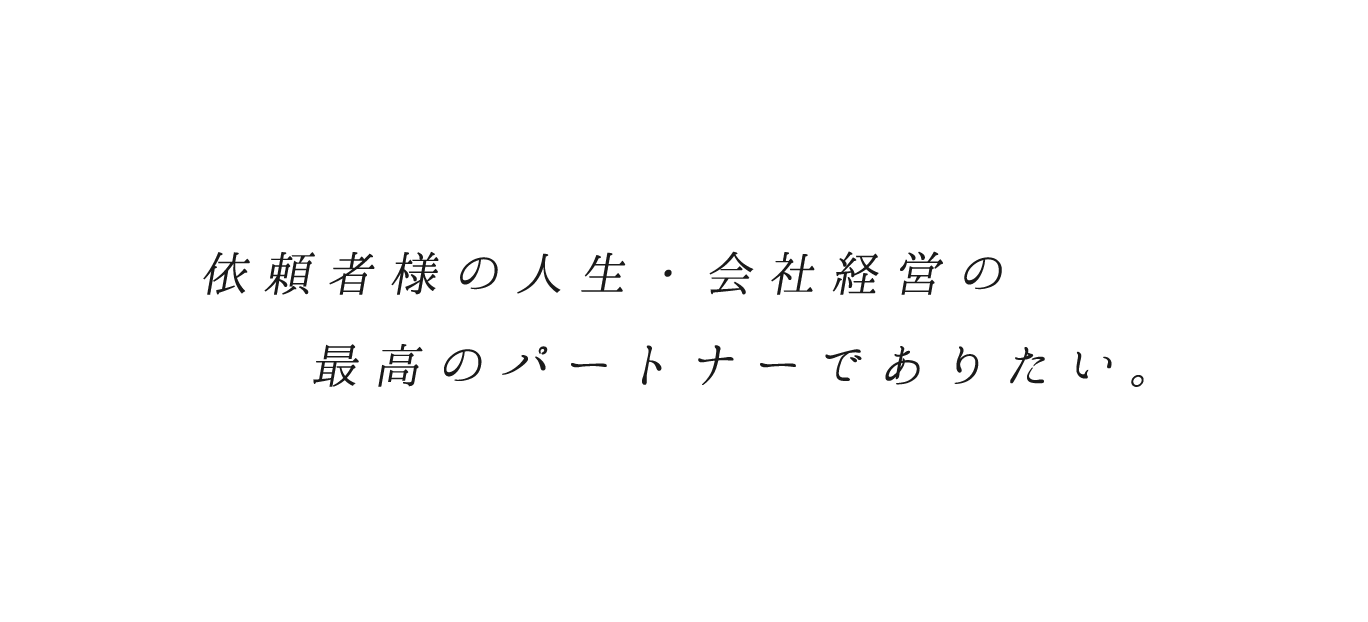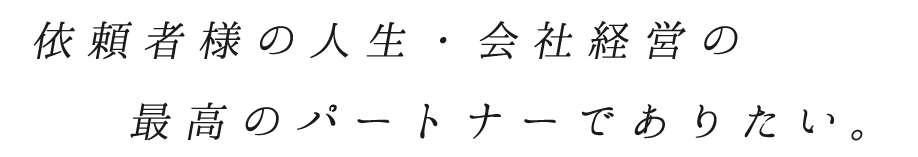よくある質問FAQ
- 完全歩合制の労働者から、コロナの影響で営業成績が上がらず最低賃金を下回るので、休業扱いにして休業補償を支給するよう求められており、その従業員は会社を勝手に休んでいます。会社としてはこのような従業員の要求に応じる義務はありませんよね?
一部リスクがありますので注意が必要です。
■完全歩合制について
まず、経営者の方が誤解されているようですが、雇用している社員に対しては、通常イメージされる「完全歩合制」(売上ゼロ=賃金ゼロなど)というのは違法です。
すなわち、雇用している以上は「最低賃金法」の適用がありますので、「完全歩合制」といってもそれを下回る賃金しか支給しない場合は、最低賃金法に違反してしまいます(最低賃金法第4条1項)。
このため、営業成績が上がっておらず、計算上算定される給与額が最低賃金額を下回ってしまうのであれば、「完全歩合制」といえども、会社は最低賃金額以上の金額を支払う義務を負います。
仮に、これまで最低賃金未満の金額しか支払ってこなかった場合は、不足分を支払う義務がありますのでご注意ください。
(なお、賃金等の請求権の消滅時効は、従前の「2年」から「3年」に変更されています(労働基準法の一部を改正する法律)のでご注意ください。)
■休業補償について
休業補償は会社都合で休業させる場合には支払う義務がありますが、従業員都合で休む場合には不要です。
したがって、会社の業務命令にもかかわらずその従業員が勝手に休んでいる場合は、休業補償を支払う必要はありません。
■業務命令違反
また、会社は従業員に対して命令をして業務に従事させる権利があり、従業員はこれに従う義務があります。
その従業員は会社の業務命令に違反していることになりますので、会社の就業規則における懲戒事由に当たる可能性があります。
このため、場合によっては懲戒処分を検討したり、懲戒処分をせざるを得なくなることを告げて出社を求めることも検討すべきです。
■感染リスクについて
ただし、注意が必要なのは、会社としては従業員が安全に働ける環境を整える義務があることです。
会社が十分な感染予防対策をしておらず、万が一従業員がコロナウイルスに感染して損害が発生した場合(死亡や後遺障害が発生した場合など)には、会社としては安全配慮義務違反に基づく損害賠償責任を負う可能性があります。
会社としては、現在の政府の方針等に従いながら、従業員が安全に働けるよう環境を整える必要がありますので、くれぐれもご注意ください。
- テレワークを開始しましたが、会社として何か気を付けることはありますか?
テレワークを導入するにあたり、会社として法的に最低限気を付けておくべきポイントをご紹介します。
■従業員の労務管理
テレワークを導入したとしても、従業員は労働基準法上の「労働者」ですので、会社としては労働基準法を遵守しなければなりません。
以下では、労働基準法上、特に留意すべき点を記載します。
①労働条件を明示すること
労働契約(雇用契約)時において、使用者は労働者に対して就業場所を明示する必要があります(労基法15条1項、労基法施行規則5条2項)。
テレワークとして在宅勤務を指示するのであれば、就業場所として従業員の自宅を明示することになります。
雇用契約書や就業規則などに、就業場所として「従業員の自宅」や「会社が指定する場所」などの規定がない場合には、就業場所についてテレワーク導入前に従業員に同意を得ておきましょう。
②労働時間の管理
会社は、テレワークを導入した場合であっても、従業員の労働時間を管理する必要があります。
すなわち、従業員の労働日ごとの始業・終業時刻を管理する必要があるということです。
また、テレワークを導入した場合には、会社が従業員の実際の就業状況を把握することが困難になります。
会社において従業員の労働時間をきちんと管理できていない場合には、後日従業員から会社に対して残業代の請求等がされるなどして、従業員と紛争に発展する可能性もあります。
そのため、会社としては、クラウド型の勤怠管理システムを利用したり、始業・就業時に電子メールや電話で報告させたりするなどして、従業員の労働時間を把握するように努めなければなりません。
③制度の変更や作業用品の費用負担について
テレワークを導入することにより、会社からすると従業員が労働時間中きちんと業務を遂行しているかを把握することは非常に困難になります。
そのため、会社としてはオフィスワークの従業員とテレワークの従業員とで賃金制度などにおいて異なる取り扱いを採用することがあるかと思います。
また、会社内での業務に必要な作業用品(パソコン等の機器や通信費用など)については会社が準備して費用を負担することが一般的ですが、テレワークを導入した際には、業務に必要な作業用品の準備や費用について従業員に負担させることがあるかと思います。
このとき、賃金制度や作業用品の費用負担については就業規則に定めておく必要がありますので(労働基準法89条2号、5号)、現在の就業規則に規定がない場合には、就業規則を変更する必要があります。
現段階ではほとんどの会社はテレワークを想定して制度設計をしていないと思われますので、ほとんどの会社で現在の就業規則等を見直す必要があります。
なお、就業規則の変更が当該従業員にとって不利益な変更になる場合には、労働組合などがなければ各従業員と個別に同意を得ておく必要があります(できれば書面が望ましいです)。
■情報管理
テレワークを導入した場合、従業員は会社外(自宅など)で会社の業務を行うことになります。
そのため、従業員が社外で会社内の情報を取り扱うことになり、社内で業務を行う場合よりも情報漏洩のリスクが高くなることが予想されます。
情報漏洩が起きた場合、流失した情報元に対する損害賠償責任や、会社としての社会的な信用の失墜など、会社として大きなダメージを受けることになります。
そのため、会社としては、十分な情報セキュリティ対策を講じることが必要になります。
以下では、会社における情報セキュリティ対策ポイントを3つの要素に分けてご説明します。
1.ルールの策定
まず、セキュリティポリシー等の会社としての情報管理のルールを策定することが考えられます。
その際には、以下の点を留意するとよいと思います。
①守るべき会社の情報を明確にする。
②ルールを守るべき対象者の範囲を明確にする。
③守らなければならないルールをできる限り具体的に記載する。
④社内の状況を踏まえて、運用や維持体制等を考慮しながら実現可能な内容にする。
⑤ルールの形骸化を避けるために、違反時の罰則などを明記する。
2.従業員に対する情報管理の教育や監督
従業員が会社外で業務を行うことにより、業務に使用する端末やUSBメモリなどの紛失や盗難、インターネット接続によるサイバー攻撃や情報の盗難などが考えられます。
そのため、会社としては、従業員に対して、
①ID・パスワードの管理方法を徹底する
②業務に使用する端末を制限する
③業務に使用する端末に特定のウイルス対策のソフトをインストールさせる
④パソコン・USBメモリや紙資料の紛失や盗難が発生した場合の報告や対応方法について周知する
など、ルールを策定するだけなく従業員に対して情報管理に関する教育を行い、従業員を監督しなければなりません。
3.技術的な対策
会社外でどのような業務を行うかによってどこまでの対策を講じるべきかは異なりますが、
①社内の情報にアクセスする際にID及びパスワードによる認証を経るようにする
②ウイルス対策ソフトを導入する
③ネットワークの暗号化を行う
など、様々な技術的な対策を講じることが考えられます。
具体的な対策としては、以下のページが参考になるかと思いますのでご参照ください。
総務省 国民のための情報セキュリティサイト
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/security/business/executive/03.html
- 新型コロナウイルスにより売上が減少しました。賃料の減額を請求することはできますか?
建物所有目的の土地の借主や建物の借主は、貸主に対して、賃料(地上権における「地代」を含みます。)の減額請求をすることが認められています(借地借家法第11条1項、32条1項)。
もっとも、賃料の減額が認められるためには、従前の賃料が「不相当」になっていることが必要なります(詳しくは、「どのような場合に賃料の増額・減額の請求が認められますか?」をご確認ください。)。
■新型コロナウイルスの影響で売上が激減したことを理由に、賃料の減額請求は認められるか
賃料が「不相当」であるかの判断においては、「経済事情の変動」が考慮要素とされており、新型コロナウイルスもその一つの事情として考慮されることになります。新型コロナウイルスが日本の経済事情に影響を与えると考えられるため、長期的に見ればその後の経済事情の変動を踏まえて賃料の減額が認められる可能性は十分にあると考えられますし、直近だけを見ても既に「経済事情の変動」が発生しているとみる余地もありますので、裁判所においても賃料の減額を認める可能性はあります。
ただ、賃料が「不相当」かどうかの判断については現時点では裁判所においても判断材料が少ないと考えられるため、法的な面から強制的に賃料の減額を認めてもらうには時期尚早であると考えられます。
■賃料減額のためにできること
上述のように、現状において新型コロナウイルスの影響により売上が激減したことを理由に賃料の減額請求が認められるかは定かではありません。そのため、各事業主様におかれましては、賃料減額のために今できることをしておくことが重要になります。
以下では、今できることの例として、何点かご紹介させていただきます。
①賃貸借契約書を確認する
不動産を借りる際には、一般的に賃貸借契約書が作成されます。そして、当該契約書には貸主と借主との間の約束事が明記されています。まずは、当該契約書に、賃料の減額請求について減額の条件などが規定されていないか確認するようにしましょう。
②貸主に対して賃料減額請求(減額の要請や交渉の申入れを含む。)を行う
賃料減額請求の効果は、借主から貸主に対して賃料減額の意思表示を行うことにより生じます。また、その賃料減額は、過去に遡ることができず、将来の賃料についてのみ効果が生じることになります。
そのため、賃料減額の効果を生じさせるためにも、貸主に対して、賃料減額の請求や賃料減額交渉の申入れを行っておくことも一つの手段です(方法については「どのような場合に賃料の増額・減額の請求が認められますか?」をご確認ください)。
賃料減額の要請や交渉の申入れを行ったとしても、新たな賃料が決定するまでの期間においては、従前の賃料を支払い続ける必要があります。仮に当該賃料の支払を怠った場合には、賃貸借契約を解除されるリスクもありますので、注意が必要です。
なお、賃貸借契約の解除は、簡単に言えば貸主と借主の間の信頼関係を破壊するほどの重大な義務違反がなければできないことになっています(信頼関係破壊の法理)。このため、1回の賃料支払の遅延だけでは解除は認められず、概ね3か月分程度が目安になると考えられています。もっとも、今回の新型コロナウイルスの影響では、通常の企業努力をしていても賃料支払の遅延を免れることができないとも考えられ、したがって3か月以上の滞納でも信頼関係を破壊していないとみる余地もあります。この辺りは実際の裁判を待ってみない限り確答は困難ですが、ただ、どうしても家賃の支払いが困難な場合には、貸主に対して詳細に事情を説明し、賃料の支払い猶予などを誠意をもって申し入れておくことで、信頼関係が破壊されていないと評価する事情の一つにもなり得ますので、このような賃料の支払い猶予の申入れも検討していただければと思います。
- どのような場合に賃料の増額・減額の請求が認められますか?
法律上、建物所有目的の借地や借家の賃料(地上権における「地代」を含みます。)や、建物の賃貸借については、賃料の増減額請求が認められています(借地借家法11条、32条)。もっとも、賃料の増額については、当事者間の契約において、一定期間は賃料を増額しない旨の特約などをすることは可能であり、当該特約は原則として法律上も有効とされています(借地借家法11条1項ただし書き、32条1項ただし書き)。そのため、賃料の増額請求を検討されている場合には、まず、このような特約が規定されていないかどうかについて賃貸借契約書を確認するようにしましょう。
(賃料の減額請求については、賃料を減額しない旨の特約は無効と解されますので(最判平成16年6月29日等)、上述のような制限はありません。)
■賃料増減額請求が認められる要件
賃料の増減額請求が認められる要件としては、従前の賃料が「不相当」になった場合とされています(借地借家法11条1項本文、32条1項本文)。
そして、賃料が不相当であるか否かの判断においては、法律の規定上、以下の事情が考慮されることになります。
①経済事情の変動
①-1公租公課の増減
①-2借地や借家の不動産として価格の上昇又は低下
①-3その他の経済的事情の変動
②近隣相場の変動
したがって、従前の賃料が不相当であるかの判断においては、現在の「相当な賃料」を算出し、比較することによって判断することになります。
もっとも、実際に賃料が不相当であるか否かの判断においては、上記の事情に限定されることなく、土地価格の推移の状況、賃料に占める純賃料の推移、当該賃貸借契約の内容やそれに関する経緯、賃料改定の経緯、契約成立からの経過期間など、請求時の事情のみならず、契約成立時の事情や契約成立から請求に至るまでの事情を総合的に考慮されることになります。
■賃料増減額請求の方法
賃料増減額請求を行う方法としては、契約の相手方に対する意思表示をする必要があります。例えば、借主が貸主に対して、賃料を減額するように書面等を用いて通知する方法が考えられます。
そして、意思表示をする際には、相手方に対して具体的な相当な賃料を明示することは法律上要求されておらず、値上げ又は値下げの要求や要請を行うことで足りるとされています。
なお、次に述べるように、増減額の請求の意思表示がいつの時点で相手方に到達していたかは重要な事実となりますので、無用な争いを生むことのないよう、差支えがなければ内容証明郵便で意思表示を行うことをお勧めします。
■賃料増減額請求の効果が生じるタイミング
賃料増減額請求の効果は、賃料の増減額に関する意思表示が相手方に到達した時点で生じることになります。そのため、仮に賃料が「不相当」になっていた場合であっても、意思表示の到達以前まで遡り、賃料の増額を求めたり、減額を求めたりすることはできないことになります。
なお、反対に、意思表示の到達時点で効果が生じていることになりますので、例えば「相当」な賃料について2年間裁判で争った後に従前の賃料が「不相当」であったという判断がなされた場合は、意思表示の到達時点から遡って過不足の賃料を精算する必要があります。また、その過不足の賃料に対して年1割の利息を付す必要があります(借地借家法11条2項、3項、32条2項、3項)。
事業を行う方におかれましては、店舗やオフィスといった賃料などの毎月の固定費を節減できることは長期的なメリットになり、今後の設備投資や事業拡大のための原資にすることが可能になります。賃料が長期間見直されることなく放置されている場合などには、賃料が適正な金額であるかどうかを確認することをお勧めします。
- 業績が厳しくなってきたため社員を整理解雇したいのですが、問題はありますか?
■整理解雇について
経営状態が悪化していることを理由とする解雇は、いわゆる「整理解雇」となりますが、ハードルが相当高いものです。普通解雇(能力が低いことなどに基づく解雇など)も難しいのですが、一般的に整理解雇は普通解雇よりも高いハードルを超えることが必要となります。
■整理解雇の要件
整理解雇は、判例上、以下の要件を満たした場合にのみ法的に有効とされています。
①人員削減の必要性があること
②解雇を回避するための努力が尽くされていること
③解雇される者の選定基準及び選定が合理的であること
④事前に使用者が解雇される者へ説明・協議を尽くしていること
以下、説明を加えます。
①は倒産必至という状況でなくとも、高度の経営上の困難から当該措置が要請されるという程度で足りるとされています。
最近では経営合理化や競争力強化のために行う人員整理でも、①の要件を充足していると判断した裁判例も増えています。
②は配転、出向、希望退職の募集などの他の手段によって解雇回避の努力をしたことが求められます。
もちろん、専門職などであれば配転や出向は難しいケースが多いように思われますが、可能性がある場合にはやはりそういったことを試みるべきということになります。
③は客観的で合理的な基準を設定し、これを公正に適用して人選をする必要があります。
基準としては、勤務成績や企業貢献度(勤続年数など)、経済的打撃の低さ(別企業での再就職が容易であるなど)等に基づいて設定することになります。
整理解雇に見せかけて特定の問題社員を解雇するようなケースでは、この要件を満たさないと判断される可能性があります。
④は整理解雇の必要性とその時期・規模・方法について納得を得るために説明を行い、さらにそれらの者と誠意をもって協議したことなどが必要とされています。
以上の基準は画一的なものではなくケースバイケースではありますが、経済的補償や再就職支援措置などによっても、各要素が補完されて解雇が有効となる可能性もあります。
しかしながら、基本的には上記①~④を満たすことが必要となりますので、ハードルの高さはお分かりいただけるかと存じます。
■自主退職
このため、基本的には自主退職していただくのがベストではあります。
業績が厳しいのであれば、休業させて休業補償を支払い、業績が回復するまで様子を見るということも一つの手段です。
従業員側としても、御社に業績回復の見込みがなく、他により給料の良い職場が見つかれば他社に転職することも検討するでしょうから、御社とその従業員の双方にとってWIN-WINの解決となる可能性もあります。
■雇用調整助成金の活用
また、休業させた場合には雇用調整助成金を活用できる可能性もありますし、特に新型コロナウイルスの影響に基づく休業の場合には、助成額も増額されています。
もっとも、助成金が支給されるまでにタイムラグがあり、キャッシュフローは悪化してしまうでしょうから、どのような手段を採ることができるかは資金状況をみて検討することが必要と思われます。
■「不当解雇」に注意
普通解雇や懲戒解雇においてもそうですが、整理解雇においても、法律上「有効」なものでない場合は、対象となった従業員から「不当解雇」と主張され、法的なトラブルになる可能性があります。
この場合、多額の解決金や賠償金を支払わないといけないことになりますので、会社にとっても大きなリスクとなります。
解雇をする場合には法的な観点から慎重に検討する必要がありますので、くれぐれもご注意ください。
なお、従業員が自主退職を申し出てきた場合には、後日争いにならないよう、自主退職をしたことの証拠として退職届をきちんと受領しておくことも重要です。
- 資金面での不安を感じているのですが、もし自己破産などをする場合は自宅から出ていかないといけないのでしょうか?
自己破産をする場合には、保有している財産を換価し、債権者に配当することになります。
そのため、原則として破産手続内で不動産を売却されることになり、自宅を手放さなくてはなりません。
しかし、一定の場合には破産手続をしつつも、自宅から出ていかなくてもよい場合もあります。
■①第三者が適正価格で購入してくれて、それを破産者に賃貸で貸してくれる場合
・自宅不動産の価格がいくらか
・自宅不動産に担保権が設定されているか否か
・ローンがある場合には残債務がいくらか
・協力してくれる第三者を見つけられるか
等々の様々な要素を考慮し、好条件が重なる場合には、自己破産しつつも適正価格で第三者に自宅不動産を売却して自宅に住み続けるという手段を採ることができる場合があります。
もちろん、この方法を採った場合、不動産の所有者の名義自体は変わってしまいますが、例えばご親族が購入してくれるような場合であれば実質的には問題なくご自宅に住み続けることが可能となりますので、自己破産をする前後で検討すべき手段の一つではあります。
ただし、注意点としては、必ず「適正価格」(法律上は「相当の対価」と表現されています。)で売却し、売却によって得た代金をその不動産の担保権者に返済してもなお余剰金がある場合には、この余剰金をきちんと保管し、破産手続の中で他の債権者に法律に従って返済する等していく必要があります。
これは、不動産が現金に換わってしまうと資産隠し等が容易になってしまって債権者が困ることになるという理由で、法律が原則として不動産を現金化することは許容していないためです。
きちんとルールを守らなければ、協力してくれた第三者の方に対する裁判等が提起されてしまうなど、大きな迷惑をかけてしまう可能性も出てきます。
したがって、このような方法を採る場合は、せっかく協力してくれた第三者に迷惑がかかってしまう結末を避けるためにも、弁護士等の専門家に相談しながら手続を進めるようにしましょう。
cf.民法424条、424条の2
第424条(詐害行為取消請求)
1 債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者(以下この款において「受益者」という。)がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。
2 前項の規定は、財産権を目的としない行為については、適用しない。
3 債権者は、その債権が第一項に規定する行為の前の原因に基づいて生じたものである場合に限り、同項の規定による請求(以下「詐害行為取消請求」という。)をすることができる。
4 債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、詐害行為取消請求をすることができない。
第424条の2(相当の対価を得てした財産の処分行為の特則)
債務者が、その有する財産を処分する行為をした場合において、受益者から相当の対価を取得しているときは、債権者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り、その行為について、詐害行為取消請求をすることができる。
① その行為が、不動産の金銭への換価その他の当該処分による財産の種類の変更により、債務者において隠匿、無償の供与その他の債権者を害することとなる処分(以下この条において「隠匿等の処分」という。)をするおそれを現に生じさせるものであること。
② 債務者が、その行為の当時、対価として取得した金銭その他の財産について、隠匿等の処分をする意思を有していたこと。
③ 受益者が、その行為の当時、債務者が隠匿等の処分をする意思を有していたことを知っていたこと。
■②当該不動産に設定された担保権の残債務額が不動産の価額に比して過大なとき
この場合には、自宅には価値がないものとして、自己破産手続における換価の対象ではなくなります。
cf.大阪地方裁判所において価値がないと評価される基準
・「2<当該不動産に設定された担保権(抵当権等)の残債務額÷固定資産評価額」のとき
・「1.5<当該不動産に設定された担保権(抵当権等)の残債務額÷固定資産評価額≦2」かつ「1.5<当該不動産に設定された担保権(抵当権等)の残債務額÷不動産の査定書の価額」のとき
■③何度か競売を試みたが、買い手がつかなかったとき
この場合には、換価が困難ということで、換価されないまま自己破産手続が終わる可能性があります。
もっとも、このような場合で自己破産手続内で処分されなかったとしても、自宅に住宅ローン等の抵当権が設定されている場合には、通常はその抵当権者によって自宅不動産を競売にかけられることになります。
以上のように、最初の①の手続を採ることができずに自己破産をする場合には、自宅を残すことは難しいと考えておく方が良いでしょう。
しかし、自宅を残しながら債務を整理できる手続もあります。
■個人再生(民事再生)
個人再生は、自己破産と同様、裁判所を利用する手続です。
他方、自己破産とは異なり、債務の一部を債権者に分割で支払うことを条件に、自宅や自動車を手元に残すことができます。
支払わなければならない債務としては、住宅ローン全額とその他の債務の一部(債務額により異なりますが、5分の1程度が目安)があります。
自己破産の場合には借金の全額を返済しなくてよくなるため経済的なメリットは自己破産の方が大きいですが、自宅を残したい場合には個人再生が有効な手段といえるでしょう。
また、会社経営者の方であれば、会社は自己破産手続によって倒産させつつも、代表者個人については個人再生手続を申し立てて、一定の財産を残すという選択肢もあります。
なお、この場合には債権者へ若干の返済をできる一定の資力が必要となりますので、経営の再建が難しいと判断した早めの段階で弁護士などの専門家に相談されることをお勧めします。
■任意整理
任意整理は、各債権者と裁判所を介さず任意で利息等の免除やリスケ等を行うものをいいます。
任意整理は、自己破産や個人再生とは異なり、裁判所を介さない手続です。
任意整理の場合には、抵当権者に競売にかけられない限りは、自宅を強制的に処分される可能性はありません。
任意整理のデメリットとしては、任意整理は各債権者と合意が成立させることが前提となりますので、任意整理に協力してくれない債権者が1つでもあると任意整理をすることはできない点にあります。
また、任意整理をする際には、利息や遅延損害金を免除してくれることは多いですが、元本を免除してくれることは少ないため、うまく交渉を行うことが必要となります。
さらに、任意整理は、裁判所を介さないものの、手元に残存する返済原資と、各債権者への弁済額を調整しながら交渉を行っていくことになりますので、相応の労力や時間が必要となる場合も少なくありません。
必要な資金についても、各債権者が納得する金額を返済することが前提の手続ですので、自己破産や民事再生に比べてより多くの資金が必要となることも多いです。
■まとめ
以上のように、必要な資金としては、任意整理>個人再生(民事再生)>自己破産ということになりますので、できる限り資産を残したいというのであれば、資金が完全に枯渇してから専門家に相談するのでは手遅れと言わざるを得ません。
実際にも、弁護士のところに相談に来られるケースの中には、資金が完全に枯渇しており、自己破産手続さえも執れないという絶望的なケースもあります。
このため、ある程度の資金が残っている段階で、現状のままの事業や生活を継続していくか何らかの手続を執るかについて、正しい知識・情報を基に検討することが有益です。
また、事業をしている場合には、早期に対策を進めれば、M&Aにより事業を継続しつつ個人の連帯保証債務を消滅させることができる場合もあり、よりよい解決を実現できるケースもあります。
現状を継続していくことに資金的に不安を感じている場合は、お早めに弁護士等の専門家にご相談なされることをお勧めします。
- 弊社のサービスは月額料金制で提供していますが、新型コロナウイルスの影響でサービスを提供することができなくなった場合、利用料金を返金しなければならないでしょうか?
この場合、まずは利用規約や契約書を確認する必要があります。
■利用規約や契約書などで、サービスを提供できないときの払い戻しについて定められているとき
払い戻し等の規定がある場合には、当該規約や契約書に従った取り扱いがされることになります。
したがって、利用規約や契約書の規定に従って対処していただくようお願いいたします。
なお、当該規約や契約書に「不可抗力の場合にサービス提供者側は責任を負わない」という趣旨の規定がなされていることがしばしばあります。この場合には、今回の新型コロナウイルスの影響が「不可抗力」といえるのかが問題となります。
休業要請をされておらず、自主的にサービスの提供を停止した場合には、「不可抗力」と認められることは難しいでしょう。
また、休業要請がなされ、これに基づきサービスの提供を停止した場合であっても、休業要請はあくまで単なる「要請」であって「強制」ではありませんので、「不可抗力」ではないと考えられます。実際、都道府県によっては休業要請に基づき営業を自粛した店舗に対して一定の売上を補償するための給付金が支給されるような制度設計がなされつつあることも考慮すると、やはり「不可抗力」に該当する可能性は低いと考えられます。
もっとも、サービスの提供者においても利用者の安全に配慮する必要があるため、休業要請の対象となっている事業で、実際においても、密閉空間か否か、過度に人が密集することを避ける余地がないかどうか等の様々な事情を考慮したうえで、安全にサービスを提供することが不可能である場合には「不可抗力」に該当する可能性もあります。
休業要請に基づくサービスの提供の停止が不可抗力によるものであるかはケースバイケースであり、一概に記載することは困難ですが、「不可抗力」に該当する余地は少ないと考えていただく方がよいと思われます。
■利用規約や契約書などに規定がないとき
利用規約や契約書などに規定がない場合には、民法に従って考えることになります。
① サービス提供者が自主的にサービスの提供を停止した場合
一般的なサービスの利用契約においては、利用者には利用料を支払う義務があり、サービス提供者側にはサービスを提供する義務があります。そのため、サービスの提供を停止するということは、サービス提供者側がその義務を履行しなかった(サービス提供者側の債務不履行)ということになります。
この場合には、サービスの提供を停止したことについて、サービス提供者側に帰責性があるかが問題となります。サービス提供者が自主的に停止した場合には、利用者にサービスを提供することができたにもかかわらず提供しなかったということになり、サービス提供者側に帰責性があるといえます。
したがって、サービス提供者は、自主的にサービスの提供を停止した場合には、利用者に対して損害賠償責任の履行として利用料相当額の返金が必要ということになります。
② サービス提供者が休業要請に従ってサービスの提供を停止した場合
この場合にも、サービスの提供を停止したことについて、サービス提供者側に帰責性があるかが問題となります。
まず、サービス提供者側に帰責性がない場合でも、今回の新型コロナウイルスのような事態では、利用者側にも帰責性がないのが通常です。このような当事者双方に帰責性がない場合について、民法536条1項では、利用者側は「反対給付の履行を拒むことができる。」と規定されており、すなわち、利用者は利用料の支払義務を負わないということになっています。したがって、サービス提供者側に帰責性がないとしても、利用者側にも帰責性がない場合は、利用料を返金する必要があるということになります。
他方、サービス提供者側に帰責性があった場合には、自主的にサービスの提供を停止した場合と同様、利用料相当額を返金する必要があります。
したがって、結論としては、休業要請に基づいてサービスの提供を停止した場合、サービス提供者側の帰責性の有無にかかわらず、利用者側に帰責性が認められない限り、サービス提供者側は利用料相当額を返金する必要があるということになります。
③ まとめ
以上のとおり、今回の新型コロナウイルスの影響を受けてサービスの提供を停止するにあたっては、サービス提供者側に帰責性が認められるか否かを問わず、利用料の返還が必要ということになります。
- 新型コロナウイルスにより休業した際に、アルバイトやパートタイマーなどのシフト制の労働者に対しても休業手当を支給する必要はありますか?
アルバイトやパートタイマーの労働者であっても、法律上の「労働者」に該当するため、「使用者の責に帰すべき事由」による休業の場合には休業期間中の休業手当(平均賃金(算出方法は後掲)の100分の60以上)を支払わなければなりません(労働基準法第26条)。
なお、ここでいう「使用者の責に帰すべき事由」とは、判例上使用者側に起因する経営、管理上の障害を含むとされており、一般的な判断基準として経営上の障害も天災事変などの「不可抗力」に該当しない限りはそれに含まれると考えられています。
そのため、シフト制の労働者に対しても、「使用者の責に帰すべき事由」によらない休業の場合を除き、休業手当を支給する必要があります。
(この点に関しては詳しくはこちらをご参照ください。)
もっとも、労働条件上(雇用契約書等の書面上、口頭、事実上いずれも)、月や週における最低出勤日数の定めが存在しない労働者の場合には、そもそも使用者と労働者間の雇用契約の内容として、労働者が使用者に提供する労働の範囲が明確に合意されているわけではないため、シフトカットをしたとしても、必ずしも休業手当を支給しなければならないわけではありません。
しかしながら、実態においては、
・「週に○日以上勤務」などが雇用契約書や労働条件通知書で明記されている
・過去の勤務実績において、「月に15日」など、一定期間にわたって決まった回数以上を勤務している
・その他、暗黙の了解で週に○日以上勤務することになっている
というようになっているのが通常であるように思われます。
このような場合には最低出勤日数の定めが明示的又は黙示的に存在すると判断され、前述のような「不可抗力」に該当しない限り、休業手当を支給することが必要になる可能性が高いと解されます。
このように、各労働者との雇用契約内容やこれまでの勤務実態等を考慮し、休業手当の支給の要否を判断することになります。
従業員のシフトカットなどをするに当たり、ご不安がある場合には、弁護士等の専門家にご相談し、個別の従業員ごとに休業手当の支給の要否について判断することをお勧めします。
【参考】
■平均賃金の計算方法
平均賃金の計算方法は以下のとおりです(労働基準法第12条)。
<3か月間の賃金総額/3か月間の総日数>
もっとも、時給制などのアルバイトやパートタイマーなどの労働者については、平均賃金を計算するにあたり、上記計算方法と以下の計算方法との比較により、金額が大きい方を用いることになっています。
<3か月間に支払われた日給や時間給、出来高払等の賃金総額/3か月間の実労働日数×0.6>
■雇用調整助成金
受給対象となれば、休業手当に対する一定の割合について助成を受けることができます(通常時は2/3、特例措置期間中は最大9/10)。
詳しくは以下の厚生労働省のホームページをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
- 新型コロナウイルスに関連して労働者を休業させる場合、従業員の賃金を支払う必要はありますか?
法律上、「使用者の責に帰すべき事由」による休業の場合には、休業期間中の休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払わなければならないとされています(労働基準法第26条)。
「不可抗力」による休業の場合は、「使用者の責に帰すべき事由」に当たらないため、休業手当の支払義務はありません。
ただ、ここでいう「不可抗力」とは、
①その原因が事業の外部より発生した事故であること
②事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故であること
の2つの要件を満たすものでなければならないと解されていますので、「不可抗力」に当てはまる場合はかなり限定的です。
例えば、通常の職場での勤務は不可能であるものの、在宅勤務などの方法により従業員を業務に従事させることが可能な場合など、多少効率が落ちるとしても休業を避けることができるような場合は「不可抗力」には当てはまりませんので、休業手当の支払が必要です。
経営者側としては、休業を避けるために最善の努力を尽くす必要があるということになります。
■労働者が新型コロナウィルスに感染した場合
労働者が新型コロナウィルスに感染した場合、法律上、労働者はその病原体を保有しなくなるまでの期間、就業が制限される可能性があります(令和2年政令第11号第3条、感染症法18条、同施行規則11条3項2号など)。
そのため、入院や指定場所での待機が要請されることになり就業できなくなる場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由」による休業とはいえませんので、休業手当を支払う必要はありません。
なお、業務又は通勤に起因して発症したものであると認められる場合には、労災保険給付の対象となります。
■労働者が新型コロナウイルスに感染した疑いがある場合
指定場所での待機が要請されず、職務の継続が可能である場合は、休業させるか否かは会社の判断となります。
たとえ発熱などの症状があったとしても、労働者が新型コロナウィルスに罹患しているか分からない時点では、やはり会社の判断となります。
このため、一般的には「使用者の責に帰すべき事由」による休業となりますので、休業手当を支払う必要があります。
もっとも、当該労働者が自身の判断で休業する場合は「使用者の責に帰すべき事由」による休業ではありませんので、この場合には休業手当を支払う必要はありません。
■労働者が新型コロナウィルスに感染したため、事業を休止する場合
上述のように、通常の職場での勤務は不可能であるとしても、在宅勤務などの方法により従業員を業務に従事させることが可能な場合や、他の業務に従事させることが可能な場合には、「不可抗力」には当てはまりませんので休業手当の支払が必要です。